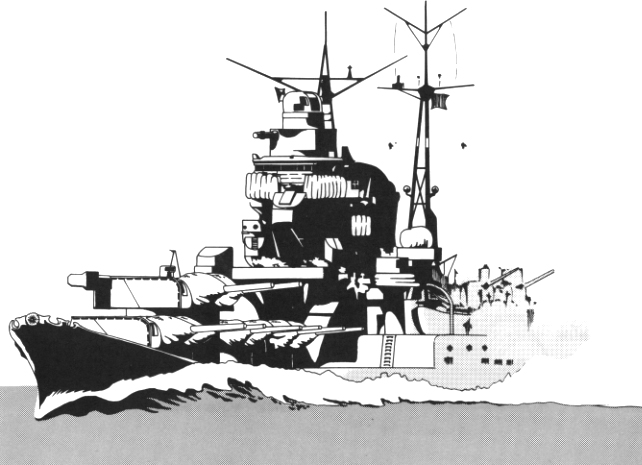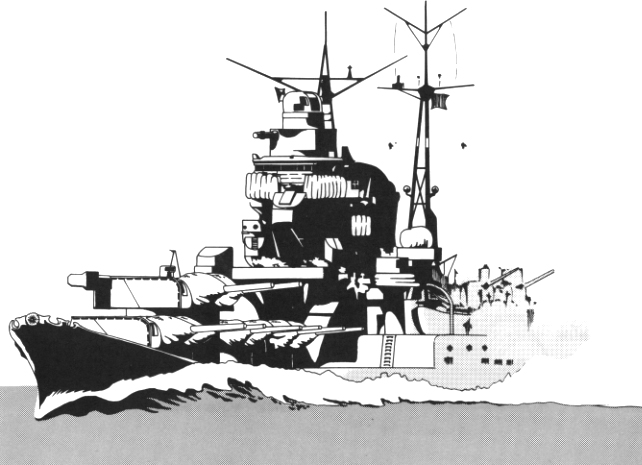キスカ島撤退作戦の指揮官、木村昌福(きむらまさとみ)中将。
サラリーマンなら誰でも「この人の下で働きたい」と思える、理想の上司なのです。
木村昌福中将(1891年12月6日~1960年2月14日)は、静岡県県生まれの日本の海軍軍人です。
太平洋戦争の海上戦闘で数々の武勲を打ち立て、特に、奇跡の作戦といわれた「キスカ島撤退作戦」を指揮し、5,183名の将兵を救出した功績で有名です。
この記事では、木村中将について語っていきたいと思います。
理想の上司・木村中将
サラリーマンは、基本的に上司ガチャなので、自分の上司を選ぶことはできません。
功名心のために部下を犠牲にするような上司の下につくと、悲惨なことになります。
前にいた職場の事例なのですが、そこの支店長は、課長が部下に行っていたパワハラを見逃していました。
課長は特定分野の業務に精通しているので、その課長がパワハラで飛ばされると、支店の業務に支障が出る懸念があり、そうなれば、支店長の出世にも響きます。
そのため、パワハラを見逃していたのです。
そんな支店長の下で働くのは本当に悲惨でしたね。

ましてや戦争の場合は命がかかっているので、もっと悲惨なことになります。
指揮官の中には、部下の兵士の命をただの数字としか思っていない人もいます。
自らの功名心のために、平気で部下の命を犠牲にするのです。
無謀な作戦を無理やり決行して、無駄な死を増やすのです。
その点、木村中将は軍人の中でも一二を争うほどのホワイト上司でした。
人間というものを徹底的に尊重していたのです。
もし会社の上司が木村中将だったら、どれだけ良かったかと思います。
木村中将のホワイト上司エピソード
木村中将のホワイト上司ぶりが分かるエピソードをいくつか挙げてみたいと思います。
士官の心構え
1941年11月15日に、木村中将(当時大佐)は、重巡洋艦「鈴谷」の艦長として、兵学校を卒業したばかりの士官候補生10名を受け入れた際の日記に、以下のような士官の心構えを書き記しています。
・自分達の勉強収得が第一 生徒の考えで兵員を殴打する等以てのほか(人格者多し 腹の出来ている者多し)
・甲板士官は乗員の世話をするつもりでやれ
・甲板士官は乗員の種々なる役目あるを考慮し必ずしも整一にはいかぬことを心得べし
・指揮監督の要点 怪我、過ちの防止
・分隊士は隊員につきよく観察すべし即ち人格有資格者をよくわきまえよ
・ただ形式、無意味に叱ったりするものあり
・若年兵の体力に関して注意せよ 保健休養の件
(キスカ撤退の指揮官 将口康浩)
このように、兵員への意味のない暴力や叱責を厳しく戒め、健康管理にまで気を配るように指導しています。
軍隊という厳しい環境にあっても、部下への気配りを徹底していたんですね。
軍隊も会社も、こんな上司がいたら雰囲気は良くなりますよね。
「撃っちゃあいかんぞお!」
1942年6月6日、ベンガル湾にて通商破壊作戦を行っていた「鈴谷」は、敵の輸送船団を発見します。
輸送船攻撃の際は、高価な魚雷を節約するために、十分に接近して砲撃によって沈めるという戦法を取ります。
ここで「鈴谷」が砲撃を開始すると、輸送船から敵兵がボートに乗って脱出を始めました。
この時、「鈴谷」艦長の木村中将(当時大佐)は、ボートに照準を合わせていた砲手に対して「撃っちゃあいかん、いかんぞお!」と、大声を出して制止したのです。
ボートが輸送船と十分な距離を取り、安全な場所まで逃れたのを確認してから、砲撃を再開して輸送船を沈めました。
このように木村中将は、人命を徹底して尊重していました。
戦争という命のやり取りにおいても、無駄に死ぬ必要はないと考えていたのです。
それは、敵も味方も変わらなかったのです。
一度でだめなら、二度三度言え
木村中将は、下士官や若い水兵に対しても分け隔てなく接していました。
若い兵士に暴力制裁を行っている古参兵に対しても、まず艦長室に呼び出して一緒にお酒を飲んで関係性を築いてから、このように諭すのです。
「精神棒はよくないぞ。棒で叩くのは馬と同じじゃないか」
「一度言って分からないときは二度でも三度でも言う。心を込めて教えれば、どんな人間でもやるようになる。といっても甘やかせというのではない。いつも威厳を持っていなければならない」
(キスカ撤退の指揮官 将口康浩)
会社にも、部下がミスをしたら「これ前も言ったよね?」と言ってネチネチと詰める上司がいます。
でも、木村中将はそういう教え方はしないのです。
加えて、暴力制裁をするような古参兵に対しても、愛情をもって接しているのです。
もし木村中将が上司だったら、どれだけ幸せかと思います。

奇跡の「キスカ島撤退作戦」
続いて、「キスカ島撤退作戦」でのエピソード取り上げてみたいと思います。
孤立する守備隊
アラスカ半島からカムチャツカ半島にかけて約1,900キロメートルにわたって延びる、アリューシャン列島。
その中に位置するのが、日本軍が占領したアッツ島とキスカ島です。
1942年6月、日本軍はミッドウェー作戦の陽動と、米国の領土占領という戦意高揚も兼ねて、この二つの島を占領します。
占領後は、守備隊として、アッツ島に約2,500人、キスカ島に約5,000人が配置されました。
翌1943年になると米軍の反攻は本格化し、5月12日に10,000人を超える兵力をもってアッツ島に上陸を開始、5月29日に日本軍の守備隊は玉砕します。
キスカ島周囲の制空権・制海権も米軍に完全に掌握され、約5,000人の日本軍守備隊が取り残されることになります。
そこで、キスカ島の守備隊の撤退作戦が計画されました。
それは、駆逐艦・巡洋艦によって守備隊の将兵を収容し、日本へ帰投するというものでした。
米軍に制空権・制海権を握られている状態で、どのようにキスカ島から将兵を撤退させるのか。
それは、濃霧です。7月に発生するこの地方特有の霧にまぎれて、キスカ島に突入するのです。
そして、その撤収部隊である第一水雷戦隊の司令官に、木村中将(当時少将)が任命されたのです。
木村中将はぬかりなく準備を進め、気象専門士官を派遣することや、駆逐艦を十艦に増強すること、そのうち一艦は最新鋭のレーダー装備の「島風」を含むことを要望します。
併せて、濃霧の中での航行訓練、給油艦からの補給訓練、将兵の収容訓練も徹底的に行います。
3本煙突の艦艇は、1本の煙突を白く塗って、2本煙突の米軍艦艇に見せかけるということまで行っています。
木村中将はキスカ島の将兵を救うために、出来ることは何でもやったのです。

「帰ろう、また来れるから」
1943年7月7日、木村中将率いる第一水雷戦隊は、根拠地である千島列島北部の幌筵から、キスカ島へ向け出発します。
7月10日の撤収予定日に向け、第一水雷戦隊はキスカ島へと近づいていきますが、現地の気象予測で霧が晴れる懸念が生じたため、7月10日の突入を断念します。
その後も、同じ理由から、突入は延期されていきます。
そして、残りの燃料から考えて最後のチャンスとなった7月15日には、第一水雷戦隊の一部からも「突入すべき」という意見が出るようになります。
しかし、木村中将は気象士官の「晴れ」の予報を信じ、一旦作戦を中止して幌筵へ帰投することを決断します。
このとき、「帰ろう。帰れば、また来られるからな。」と語ったといわれています。
幌筵に戻った木村中将は海軍上層部からの猛烈なバッシングにさらされますが、冷静に再出撃のチャンスをうかがいます。
そして7月22日に、第一水雷戦隊は再度キスカ島へ向け出発します。
米軍の哨戒機の圏外にとどまりながら天候を見極め、7月29日にキスカ島へ突入することが決まります。
その日に米軍がキスカ島の包囲を解いたという幸運も重なり、第一水雷戦隊はキスカ島へ突入して5,183名の将兵を収容、キスカ等の撤退作戦を成功させたのです。
「人柄」が作戦を成功させた
もし、7月15日に第一水雷戦隊が突入していたらどうなったか。
一番近い米軍飛行場の天候は晴れだったため、米軍の哨戒機に発見されていた可能性もあります。
そのため木村中将は、米軍側に発見されないための、より確実な選択肢を選んだのです。
海軍上層部の中には、作戦成功の有無よりも突入の有無が大事だという意見もありました。
勇猛果敢であることが評価されたのです。
もし、木村中将が功名心を優先していたら、15日に突入していたかもしれません。
しかし、木村中将は功名心よりも人命を優先して判断をしたのです。
徹底して人間というものを尊重していたのです。
このような人柄だったからこそ、部下は木村中将を慕って、最高の働きをしたのではないでしょうか。
キスカ島の撤退作戦というプロジェクトを成功させたのは、木村中将の人柄によるところも大きいでしょう。
まとめ:「人柄」も大切な能力
日本海軍は、ハンモックナンバーと呼ばれる成績順位で将来の出世が決まります。
木村中将の海軍兵学校での成績順位は、118人の同期の中で107番でした。
木村中将は、兵学校出身者の出世コースに乗っているとは言えなかったのです。
ところが、木村中将を慕う部下は最高の働きをして、そのこともあって木村中将はキスカ島の撤退作戦をはじめ数々の功績を上げることが出来ました。
人の能力は、テストだけで測れるものではありません。
木村中将のような「人柄」も大切な能力なのです。
人に慕われないような上司では、その下で働く部下のパフォーマンスを最大限に高めることはできません。
組織としての成果を出すことはできないでしょう。
そのことは、木村中将の生き方からよく分かります。
木村中将のような人こそ、「理想の上司」と言えるのです。